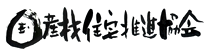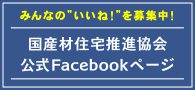「朴訥の論」コラムの記事一覧
改築後9年経っての不具合
【暮らしのお片付け上手, 朴訥の論】
今年の春頃に、けたたましいアラーム音がキッチンから聞こえてきました。稼動させていた食洗機の表示がチカチカと点滅しています。使い始めて9年目に入ったところ。
インターネットで、扉に書かれている品番と点滅表示で検索すると、「庫内の防水パンに水が漏れている」との事。すぐにメーカーの修理に連絡し予約したのですが、もしや自分で解消できないものかと、また検索をかけました。すると同じ事を考えている人がいて、その書込みの解説を見ながら、私もドライバー片手に進めると防水パンの水を排水することができ、1日程乾燥させると点滅も消え、使える事になりました。しかし、再び稼動させたら、排水の時にアラームがなったので潔くあきらめました。結局、庫内の排水ホースが破れていました。
修理の日、どのように修理されるか、職人さんに嫌がられるかなぁと思いつつ、じっと横で見ていたら、
「同じ事をしようとしないでくださいね。故障のもとですから。」と釘をさされました。
そして先日、システムキッチンの排水がとうとう、ほとんど流れなくなりました。数年前にも詰まって困り、アルカリの洗剤を使って対処と予防もしていのに、もうどうにもなりません。思いきってキッチン下のトラップ全部を取り外して確認をしたら、トラップ下のジャバラホース部分内部が白い固形の油がびっしりで、竹串の太さぐらいの水しか通らない状態でした。
庭にて、トラップ一式にできるだけの水圧をかけて洗浄をして、スッキリ解決です。純石鹸を使うので、仕方ないトラブルで、ジャバラ配管ではできませんが、定期的に実施されるマンションの高圧洗浄がうらやましいです。改装して9年経つと色々と不具合がでてくるものですね。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2025年木族8月号より~
酷暑の夏に・・・
【朴訥の論】
39℃という北海道の気温に誰もが驚愕し、地球温暖のひっ迫を突き付けられたようだ。皆様にはこの酷暑をいかがお過ごしでしょうか。
杉・ヒノキを壁や床板として利用して40年になる。当初は乾燥の度合いも甘く、最初に馴染みの居酒屋で壁板として試作したが、乾燥するにつれ實(さね=板と板をつなぐ凸凹)が外れてしまった。ただ、居酒屋は杉板を張り替えることもなく35年の営業を杉板とともに全うした。
これが住宅であれば、風情が良い、味があるなどとは言っておれない。長い年月をかけ板材は乾燥、製材など可能な限り反りや曲がりのない製品均一化の努力を重ね今日に至っている。
当初は節の有る無しで価格差も大きく、節を嫌わずに使うことを推奨していた。ところが板材を生産する側からすれば節ありは抜け節の処理に手間がかかり割に合わない。最近では上小節(小指の先ほどの節)の施工が増えている。
木材は乾燥材であっても冬の乾燥期には痩せ、梅雨時には湿気を吸収し太るため、一年を通して様子をみる必要がある。その調湿効果こそ木材の利点でもある。工業製品であれば痩せも太りもしないため施工性はいいが、調湿効果は薄い。どちらを選択するかは自由であるが、長短含めて理解して欲しいものだ。
陽炎(かげろう)が立つほどの好天気の日に大阪で地鎮祭が行われた。古式に則(のっと)って厳かに執り行われ、参列者それぞれが工事の無事を願った。現地に行くまで気づかなかったが、その場所は36年前に新築を建てた2軒隣だった。ところが通りを探してもその家は見当たらず、2軒隣は更地になっていた。
国産材の活動を始めたころ、事務所下にあった喫茶店のご家族と懇意になり、ご自宅を建て替える相談をいただき、前理事長(故)の熱烈な勧めにより骨太の国産材の家が完成した。ご家族の要望でもあり協会では珍しい洋風の住宅と、吹き抜けにある階段支柱の太い杉丸太が自慢だった。阪神淡路の震災から数年後ご主人が病で亡くなり、夫人は故郷で喫茶店を開業するため、その家を手放された。
解体するには惜しい家であるが、新しく住む人にとっては価値がなかったのだろう。更地と気づいた瞬間、何とも言えない感情が湧きあがり、寂しさがこみ上げる。家にもそれぞれの事情があり、その運命を辿るが、家を解体するということがお施主さんにとってどれほど心痛むことか、今更ながら思い知らされた。
ご無沙汰ばかりの夫人に逢いたくなった。
(国産材住宅推進協会・代表=北山康子)
~2025年木族8月号より~
ブルーオーシャンを泳げ
【朴訥の論】
ベランダの小さなサボテンがピンクの花をつけ、お天気のありようで開いたり窄(つぼ)んだりまるで意志があるようで健気に感じる。
先日、条件付き土地を購入し現在建築中の友人から相談があった。年明け早々に工事着工したものの、工事が進まずストップしているという。理由は大工さんがいない為だとか。
建築関連業種の人材不足が言われて久しいが大工職は2013年の40万人から2022年には29万7900人と、ここ10年で10万人も減少している。その建築メーカーさんも受注を手一杯受けたものの職人さんの手配が追い付かず、やむを得ず工事が中断していると思われる。
建築は出来る箇所から先にやればいい、というものでもなく、施工順が後先になれば何らかの支障をきたす。
大工さんの高齢化と、若い大工を根気よく育てるゆとりある親方も少ない。働き方改革が職人の世界にも浸透しているのか、一昔前のように早朝から夕方暗くなるまで働く職人さんは殆どいない。また、時間外の作業を容認する現場も存在しない。
一般的に都市部では、作業時間を朝8時~夕方5時迄と制限が求められ、一部では朝9時からという地域もある。マンションでは音の問題もあり朝9時~夕方5時迄となり土、日の作業も禁止されている。
稼働時間が6時間であっても一日の工賃は変わらず、作業日数が増えることになる。工程が逼迫しても、稼働時間の制約で頑張ることも出来ない。
人を育てるには資金力と忍耐がいる。また最近の若者の傾向として2、3年で転職を繰り返すことが多く、イロハのイを覚えた段階で手放すことになる。特に技術職が実を結ぶには相当の時間を要し、育つ方も育てる方も忍耐とやる気がなければ成り立たない。
40年近くお世話になっている畳屋さんがいる。周りの畳屋は殆どなくなり結構忙しくしているが、歳と共に畳の運搬が堪えると話されていた。最近、若い方が入ったと聞けば、何となくホッとする。
大工・左官・木製建具・瓦屋根屋さんなど、日本建築に欠かせない長い業績のある職種ばかり、一代で終わらせるにはあまりにも惜しい。
あと一踏ん張りし、抜け出た先の大海原を悠然と泳ぎたいものだ。
残されしものが報われると信じて。
(国産材住宅推進協会・代表=北山康子)
~2025年木族6月号より~
小さな声が重なって
【朴訥の論】
先日、富田林の「つながりサポートセンター」さんの改修工事の完成引渡しに同行した。
食品ロスを軽減することと、地域の人の食のサポートとして、不要となっている食材を提供する企業や商店から食材を受け、各こども食堂等に適切に配布することを目的とされている。また、センター内でボランティアによる食堂も運営し、子どもに限らず様々な事情で食に恵まれない高齢者にも提供されるようだ。
ここまでの形に地域をまとめ上げ、行動されていることに感動する。各地で同じような活動が広がりを見せていることが何より嬉しい。
先月、1人いる母方の叔父から電話が入った。
「わし1人になってしもてなぁ」。奥さんは認知症に要介護となり長男の近くにある施設に入所したという。
叔父は高度成長期に腕のいい造付け家具職人として、繁忙な時期を送った人だ。ただ酒癖が悪く母を随分困らせていた。
最初の奥さんは女児(Kちゃん)を未熟児で出産した後、体調が回復しないまま亡くなってしまった。未熟児で生まれたKちゃんは障害児で、医師から長くは生きられないと宣告されていた。
その後、迎えた後妻さんは、Kちゃんに実母と変わらぬ愛情を注ぎ、あれほど周りを困らせた叔父も後妻さんには感謝しかなく、驚くほど穏やかに変化していった。
後妻さんはKちゃんが43歳で亡くなるまで寄り添い、毎日、障害児の作業所まで自転車での送り迎えを欠かさなかった。意識がなくなるまでKちゃんは「お母さん」の手を離さなかったそうだ。
ひっそりと送る家族葬を想像していたが、それを覆すように作業所の先生や友達が花を手向け別れを惜しんだ。
Kちゃんがどれほど多くの人と関わりをもって生きていたかを目の当たりにし、驚きとともに心の和らぎを覚えた。言語もままならないKちゃんが後妻さんにそれほどまでに心を開き、信頼するには、言葉で表せないほどの苦労があったことだろう。
Kちゃんが亡くなり2,3年が経った頃から、糸が切れたように後妻さんの体力は落ち、認知症状が現れたという。叔父は渋ったようだが長男に諭され介護施設に入所された。
考えてみれば叔父夫婦はKちゃんに育まれ、やがてかけがえのない絆で結ばれていったのであろう。Kちゃんの短い人生を輝かせたのは、家族のみならず彼女に触れ合った全ての人たちだった。
こども食堂の大きな功績は、食に留まらず小さな声がけの積み重ねかもしれない。
(国産材住宅推進協会・代表=北山康子)
~2025年木族4月号より~
進化する土地探し
【暮らし下手, 朴訥の論】
家づくりに携わるものとして、最も頭を悩ませるのが予算と土地の確保です。社会情勢に合わせてじわじわと土地の価格も上昇しており、予算内で良い土地を見つけるには、今まで以上に体力と時間が必要になってきています。
今までの土地探しの方法といえば、複数の土地情報サイトを定期的にチェックして公開物件の情報を地道に収集するか、不動産屋さんを巡って、非公開物件を足で探すかが基本でした。建築士事務所民家でも、提携する不動産屋さんと地道な土地探しを基本としていましたが、なかなか良い物件をスピード感を持ってご紹介することが出来ずにいました。
地道で時間のかかる土地探しに何か方法は無いかと考え、今年から土地探しのアプリを導入することを決定しました。手元のスマホを使って気軽に土地探しができ、土地情報サイトだけではなく、不動産屋さんしか見ることが出来なかった非公開物件も掲載されているため、土地探しのお手伝いに強力なツールになると考えています。
連絡を頂き建築士事務所民家からアカウントを発行すれば無料で使えます。土地探しの方法も進化しており、判断力とスピードがますます重要になってきました。同じ土地を求めるライバルに差をつけるためにも是非活用して頂ければと思います。
3月8日に土地探しセミナーも開催されますので、是非合わせて参加頂ければと思います。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2025年木族2月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (2)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (2)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (94)
- 酒と家具とインテリア (2)