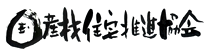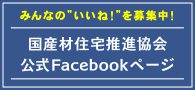「暮らし下手」コラムの記事一覧
設計の先にあるものが
【暮らし下手】
学生時代、有名な設計事務所に入ったり、大きな設計会社やメーカーに入ったりと、設計の仕事にも様々な夢のある方向性がある中で、「中津さぁ、今の時代に建築家になったってしゃあないやろぉ」という言葉を添えて、今の「工務店での住宅設計」という、自身の設計としての方向性を面白がって後押ししてくれたのが吉井先生でした。
それから約10年が経って、そろそろその後の報告をと、先日初めて新築の完成見学会の案内を送りました。
見学会当日、外観を眺めながら一通り設計の経緯やポイントを説明し、間取りをなぞりながら質疑を受け、先生の視線が止まる度に、あれ何か変な所あったかなと、ちょっとドキッとする。素材の使い方、目地の方向、金物の納め方、ここはこうなるよね、こっちはもっと違った表現もあるよね。と建築談義を交えながらの緊張の講評は、気づけばあっという間に3時間が過ぎていました。
しかし本番はここから。今までのなんだか難しい格好いいモノを作りデザインする事の話を「見た目の格好良さや美しさは個人の嗜好の問題だから」とサラリと一蹴して、工務店としての設計の先にあるもの(建築家がつくる作品のような家ではなく、ものを作る過程やその先の関係も含めて)で何ができるかだよね。その可能性が楽しみです。と、遠く、先に繋がる課題を明確に残して頂きました。
確かに、設計においても情報が溢れ、雑誌で見たカッコイイ家を簡単に真似が出来るこの時代に、力を入れるところはそこじゃないよなぁと、さすが先生。工務店だからできる家づくりって何だろう。これから出会う沢山の方と一緒に実現して行きたいと思いました。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2025年木族4月号より~
進化する土地探し
【暮らし下手, 朴訥の論】
家づくりに携わるものとして、最も頭を悩ませるのが予算と土地の確保です。社会情勢に合わせてじわじわと土地の価格も上昇しており、予算内で良い土地を見つけるには、今まで以上に体力と時間が必要になってきています。
今までの土地探しの方法といえば、複数の土地情報サイトを定期的にチェックして公開物件の情報を地道に収集するか、不動産屋さんを巡って、非公開物件を足で探すかが基本でした。建築士事務所民家でも、提携する不動産屋さんと地道な土地探しを基本としていましたが、なかなか良い物件をスピード感を持ってご紹介することが出来ずにいました。
地道で時間のかかる土地探しに何か方法は無いかと考え、今年から土地探しのアプリを導入することを決定しました。手元のスマホを使って気軽に土地探しができ、土地情報サイトだけではなく、不動産屋さんしか見ることが出来なかった非公開物件も掲載されているため、土地探しのお手伝いに強力なツールになると考えています。
連絡を頂き建築士事務所民家からアカウントを発行すれば無料で使えます。土地探しの方法も進化しており、判断力とスピードがますます重要になってきました。同じ土地を求めるライバルに差をつけるためにも是非活用して頂ければと思います。
3月8日に土地探しセミナーも開催されますので、是非合わせて参加頂ければと思います。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2025年木族2月号より~
そんな思いも伝えていきたい
【暮らし下手】
10月から11月にかけて京都、兵庫、高知とそれぞれに特徴のある木材産地を廻りました。
京都は北山杉でも有名な京北エリアにある【京北プレカット】さん。規模も大きく、在来からCLT、特殊加工と優れた加工技術を持つ工場でした。課題はその規模と安定した供給を維持するための人材の確保。現在は対策として積極的に外国人の雇用を行い、日本人よりよっぽど真面目で学習が早いと評判だそう。材料加工の打合せで訪れましたが、精緻な加工設計技術と材種・産地の対応力には驚きました。
兵庫は宍粟市にある【しそうの森の木】さん。木材の流通過程の改革にはじまり、品質を第一に考えた乾燥技術(真空乾燥・天然乾燥)の導入、使い手のニーズを意識した特色ある木材製品を開発している。そこまでやるのかと言うほど考え抜かれた製品と品質の理由が、一貫して木を無駄なく大切に使い、材の真価を見出すことであるのが嬉しい。実は木族でも15年前に取材を行っており、変わらない改革意欲に感銘を受けました。
高知はお馴染みの【ゆすはら町森林組合】さん。高い環境意識と品質、顔の見える家づくりを森から進めており、山の管理から製材・加工までを一貫して行っています。12月棟上げの新築の柱の伐採式で訪れましたが、丁寧に森林組合のスタッフの方が森を案内して下さり、森林組合の建物の廊下には、今まで伐採式で訪れた方々の写真が飾られて、まさに顔の見える家づくりがそこにありました。環境意識や生産者と消費者を繋ぐ活動は、宿命のように地道な活動を長く続ける必要がありますが、実直にその活動を進めている産地の姿がいつも励みになります。
こうして産地を廻ると、それぞれに全く違った課題と取り組みがあるのが解ります。木も産地だけでなく、誰がどんな思いで生産しているのか、そこまで伝えなければなと、改めて感じる機会でした。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2024年木族12月号より~
素朴で無骨で愛らしい出来
【暮らし下手】
◆大工家具
国産材住宅で設計施工した家に合わせて、一緒に家具も作れないかとよく問い合わせをいただきます。
家具の作り方にも大きく2パターンあり、1つは、家に合わせてデザインした家具を家具職人さんに造作を依頼する方法。チークやウォルナットなどの堅木を使い、繊細で、金物など細部にこだわった思い通りの家具を作ることが可能です。
対して、現場の大工さんが作る大工家具も人気で、比較的低価格で家と同じ素材・産地で家具を作ることができます。杉やヒノキがメインの素材となり、道具も異なるため家具職人の造作家具より無骨で素朴な印象になりますが、その無骨さがまた愛らしくもあります。
先日、イベントスペースのための什器(椅子としても展示台としても使えるスツール)をご依頼いただき、せっかくなので、友人の設計事務所と共働でデザインすることにしました。
国産材をテーマに価格を考慮して杉のパネルを主材として計画し、お互いの仕事が終わった後に夜な夜な缶コーヒーを片手に1分の1で段ボールや端材を継ぎ接ぎしながら、強度や予算、使い心地になんとか納得の行くデザインが完成しました。
スッキリとした見た目の割に、ホゾや相欠ぎを多用しているので、いざ作ってみると大工さんの造作時間が予定の倍以上かかってしまい赤字ギリギリでしたが、仕上がった家具に「感動」という言葉を沢山頂いて喜んで頂くことができました。
なんてことはない素朴でシンプルなスツールですが、考えただけの価値はあったな、と改めてモノづくりの楽しさを実感しました。
低価格で手軽に家具を買える時代になりましたが、長く使うベッドや学習机など、自身の生活に合わせて家具を作るという選択肢もオススメです。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2024年木族10月号より~
運命を感じた椅子たち
【暮らし下手】
私がインテリアに興味を持つきっかけになったのは、1軒の家具屋さんでした。当時アトピーに悩まされ東京の病院に通っていたのですが、その道すがら立ち寄ったお店で、アメリカの巨匠デザイナー、チャールズ&イームズの椅子に出会い、その世界にどハマリしたのです。
ヴィンテージ家具のショップが立ち並ぶ目黒通りを何往復もし、ネット検索でショップを見つけては立ち寄り、気が付けば家の中はアメリカンな家具だらけに。
シャギーカーペットを敷いて大きなモンステラを置いてピンクパンサーのポスターを飾り、薄暗い照明の中でイームズに腰かけては安いコーポで悦に浸っておりました。思い返せば黒歴史です。
今まで数々の運命的な椅子に出会い、手放してきました。頻繁にある運命など運命ではないとやっと悟った気でいますが、昭和レトロ家電においては、未だすぐに運命を感じる次第です。
(建築士事務所民家・設計部=矢野祐子)
~2024年木族8月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (1)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (1)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (92)
- 酒と家具とインテリア (1)