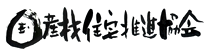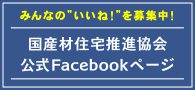「暮らし方上手」コラムの記事一覧
続けたい「国産材」の話
【暮らし方上手】
情報化社会と言われてからかなり時間が経過し、ネット検索で簡単に調べたい事がわかるようになりました。でも、なかなか見つけられない事もあります。
先日の堺セミナーでお話しをした後の休憩時、参加された方から「農作物の種の話をご存じですか?」と国産材の話から思い出されたご様子で、お話が始まりました。
「種には大きく固定種とF1種(一代限りの種)の2種類があり…とのご説明で…詳しいことは石井吉彦著「まず種から始めよ」に書いてありますよ」と勧められました。
もう既にご存じの方もおられるかもしれませんが、その本を読むと私の知らないことばかりです。石井さんは26年前から活動されており、この本も13年前に出版されたものです。
土と農薬に気をつければいいだけでなく、種にもこだわらないと安全な野菜が入手できないのかと驚きました。なぜこのことがもっと広まり当たり前にならないのか…。
3月にSNSで私発信のZoomセミナーを開きました。参加者ゼロを覚悟していましたが、嬉しいことに知人一人から申し込みが。具体的な住まいづくりの計画は無いようでしたが、自然素材に興味があり参加されました。
感想に「そもそも木造住宅の構造部分が国産材なのか、輸入材なのかも知らなかったし、国産材を使うという選択肢があることすら知らなかった。以前新築も視野にいれながら土地探しをした時にそこまでたどりつかなかった。(現在築浅の中古住宅にお住まい)」とありました。確かに知らなかったら探しようも選びようもないです。
国産材住宅推進協会主催のいつものセミナーでは、国産材を選んで来られる方のご参加ですが、今回未だ知らない方一人でも、国産材のことを知ってもらって、セミナーを開催したかいがありました。
あらためて、知って選ぶということは大切なことだと思います。自分のアンテナをたてて選択肢を増やし、納得のいく暮らしをしたいものです。
石井さんが種の話をするように、私も国産材の話を小さな声ながら、国産材の話を続けていきたいものです。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2025年木族4月号より~
代々受け継がれるべき木造住宅
【暮らし方上手】
先日テレビにて、「木造住宅は20年から30年しか持たないので・・・」という言葉が耳にとまりました。固定資産税の基準で木造住宅は22年で課税価値がゼロになる。それを参考にしての発言かと思いますが、実際はどうでしょうか?
築150年の古民家の改装の設計をした時に実感した事が3つあります。
1つめは、代々住み続けるには、その家を愛しながらメンテナンスをし続けることです。ご家族でとても大切に家を守り、次の世代に渡す事をよく考えられていました。
2つめは、床下がよく乾燥していることです。家は床下に湿気があると傷みが早くなります。このお家の床下はとてもカラリと乾燥し、洗い工事の時に水が溜まるぐらいに乾燥しても、みるみるうちに乾いていくほどでした。
3つめは、構造が国産材であること。150年前ですから輸入材はなく、オール国産材です。ただ、昭和40年代に改装された時に松の大きな梁に外国産材の柱をとりつけたら、その柱からそれまでに無かったシロアリの被害に遭われました。日本の風土に合った国産材を使う事が家の寿命も延ばすのかと思います。
私たちは50年ぐらい生きた国産材をよく乾燥させて骨組の材に使ってます。最低その倍、100年ぐらい以上は問題なく持ちます。ただし、床下の乾燥に留意し、こまめなメンテナンスが必須です。
国産材で建てることによって、長持ちで代々受け継がれていく家になるかと思います。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2025年木族2月号より~
「換気」そして「調湿」を重視
【暮らし方上手】
灼熱の夏が終わり、短い秋を経て冬が来ました。夏の暑さから解放され、季節の移ろいを感じる喜びはありますが、気温に合わせての衣服や暮らしの調整は慌ただしいものです。
来年4月から建築基準法等の省エネ促進の改正で、省エネ基準の適合が義務化され、住まいは益々高気密・高断熱が当たり前になっていきます。
温熱環境を考えると、そうあるべきと思いますが、何かしら息が詰まるように感じる人も多いと思います。秋の心地よい風を感じる日は短く、春は花粉が気になり閉め切ってしまい、夏も窓を閉めて冷房をかけ、冬もほぼ開けること無く暖を取ります。一年を通して、窓を開けて換気をする日数は少なく貴重に思います。
そこで、肝心になるのが換気方法です。機械に頼るのに違和感は残りますが、一応はシックハウスを防ぐために、2時間で家の中の空気が入れ替わる風量の換気扇と給気口の取り付けが義務化されています。そのおかげで室内の湿度の調節に一役かっています。
他にも換気扇には、外気温度に左右されない熱交換タイプや、全館空調の方法もありますが、メンテナンス性をよく考えて採用してほしいところです。
生活をしていると、キッチンの煮炊きやお風呂の湿気、人の呼気でも湿度は上がります。上手に換気扇を使用することが大切になりますが、機械だけに頼らず、内装に調湿作用がある素材を使うことも重要で、合板の床でビニールクロス仕上げの壁天井のお部屋では、それこそ息が詰まる心地です。
高気密高断熱の家こそ、調湿作用の優れた杉材を床や天井に、漆喰ベースで竹炭とゼオライト(天然鉱物)が入った左官材料の「そよ風」を壁に採用し、快適な住まいにして欲しいです。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2024年木族12月号より~
残そう伝統技術「長ほぞ込み栓」
【暮らし方上手】
巨大地震が危惧される中「私の家は大丈夫でしょうか?耐震等級3以上あるのでしょうか?」と大阪府で5年前に新築したお施主様からお問合せがありました。
日進月歩の建築業界、建築時期により性能に対する考え方も変わっています。今の民家の新築では許容応力度計算した耐震等級3(建築基準法の1.5倍の強さ・最高位)は標準仕様となりましたが、ちょうど5年前は構造計算ソフト採用の過渡期で、その方の家は手計算の構造計算で、確認をすると耐震等級2(建築基準法の1.25倍の強さ)ぐらいでした。テレビなどで耐震等級3以上ないと大きな被害を受けると煽られているようですが、民家の住まいづくりでは、耐震等級3でないからといって不安になることはありません。
民家(国産材住宅推進協会)の住まいづくりの特徴でもある、全ての柱頭柱脚に古くから日本建築に使われた伝統工法=横架材(梁や土台)に細い穴を開けて、長ほぞという突起がある柱の先をそこにはめて硬木(樫や栗の木)の栓を横架材の横から差し込み、横架材と柱を繋ぐ「長ほぞ込み栓」=を開設当初から採用しています。
現に、阪神淡路の震災の時は耐震等級1(建築基準法レベル・最低位)ぐらいの時代でも被害はなく、地震がひどかった東灘区の家も漆喰塗りの壁にヘアクラックが1本入っただけで、棟上げ直後の家を計測すればほとんど狂いがなかったと聞いています。
もちろん「長ほぞ込み栓」が全てではありません。ただ、現在「長ほぞ込み栓」を採用している工務店さんは希少ではありますが、少なくとも構造に有効に働いていることは間違いなさそう。伝統技術の一つとして継承していきたいものです。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2024年木族10月号より~
冷房が苦手でも命のためには…
【暮らし方上手】
年々暑さが増しています。毎年勧めていたのですが、とうとう夫も通勤時に日傘デビューをしました。日傘男子も最近よく見かけるようになりましたね。
「家のつくりようは夏をもって旨とすべし」とする日本の古い民家は窓も多く風通しがよく、藁葺(わらぶき)等の断熱性能の高い屋根材で、天井裏も広く取られ、軒も深くして夏を木陰のように過ごせるように造られていました。
しかしそのような民家でも、今の夏は外気温が高く、風を通しても特に日中は熱風で涼しくは暮らせなくなっています。
築49年の木造2階建ての我が家は、断熱材が入っていません(改装の時1階の一部に入れました)。日中に冷房をかけている1階から階段を上がると頭から全身へ暑さが広がり、外気温度より高い2階は地獄です。2階の寝室は就寝時間より早めに冷房を入れて冷やさないと寝ることができません。夏場は屋根の断熱材が大切だと実感しています。
数年前に友人から聞いた話では、マンション一人暮らしの40代女性が冷房の冷たい風を嫌い、ベランダの窓を開けて扇風機で暑さを凌いでいたようです。しかし、その結果、熱中症で亡くなられたようです。水分補給の不足が原因かもしれませんが、その話を聞いてから躊躇なく室温が上がれば冷房を使用しています。私も冷房の冷たい風は好きではないので、嫌う方のお気持ちはよくわかりますが、今の暑さでは、上手に冷房を使うことが最善かと思います。
直接冷たい風が当たらないように、冷房の温度を調整し、足元を冷やさないようにと工夫しながらこの夏を凌いでいただきたいものです。
最近の気密性や断熱性が高い家でさえ、一度暑さが室内に入ると保温してしまうので、上手に冷房を使うことが前提になります。昨年、冷房が苦手で、Tシャツ等を軽く水で濡らし、気化熱(水が蒸発する時に熱を奪ってくれる)を利用して涼しく過ごされている方からもお話を伺いました。ご参考にして下さい。
(建築士・ライフオーガナイザー=細江由理子)
~2024年木族8月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (2)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (2)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (94)
- 酒と家具とインテリア (2)