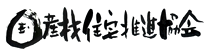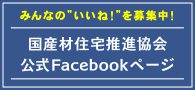「いい木、いい家、いいくらし」コラムの記事一覧
無下にしない気持ちが素敵
【いい木、いい家、いいくらし】
八百万(やおよろず)の神がいる日本。土地や場所に触れるお仕事をしていると、おのずと多くの神様仏様という見えない御施主さんの存在に遭遇します。敷地の井戸に、または土地に昔から住んでいたり、寺社仏閣のように社が建っていたり。
現在、お寺の庫裡の増築や別件新築の講堂の計画があり、設計中の大きな街道沿いの家の敷地には小さな祠があり。と様々な見えないお施主さんを含む打合せが進行中です。
旧街道沿いの家の敷地に住む龍神さんの祠は、維持の難しさから取り壊しも考慮しているところ、お施主さんもどうするべきか?と悩む中、設計としても安易に口出しはできない。
たまたま生駒山の山頂に住む旧知の知人のお寺が龍神さんをご本尊としており、これも何かの縁かと相談に行きました。
「取り壊してもええんかな?」と聞けば、「そんなの龍神さん次第やけど、勝手に追い出されたら俺でも怒るで。」と笑いながら住職、確かに。お伺いを立てて、清めて、場所を設けてと、様々手順もあり、総じて言えば、人間と全く同じ。恭(うやうや)しく丁寧に、こっちの都合で動いてもらう以上、次の転居先も手配して、納得してもらえるような手筈を整える。「じゃ、そうなった時はよろしく。」と生駒山頂の眺めの良い転居先を確保して戻ってくることができました。
そういえば、今まで地鎮祭を行わなかった家は無いし、井戸をなんの手立ても無く潰(つぶ)したことはありませんでした。これだけ合理化された現代でも、不思議と誰の心の中にも神様仏様を無下にしない気持ちがあるのが素敵だと思う。見えない人の心と同じように、見えない存在を大切にする気持ちを忘れないようにして行きたい。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2025年木族8月号より~
木の香りに心を傾けて・・・
【いい木、いい家、いいくらし】
■聞香(もんこう)
インドネシアで家具屋さんの並ぶ通りを歩いていると、木端(こっぱ)が詰められたガラス瓶の並ぶお店を見つけました。聞けば東南アジアそれぞれの地域で得られた貴重な香木を量り売りしてくれるお店だそう。
昔、正倉院に納められている蘭奢待(らんじゃたい)の匂いを再現したとするお香を嗅いだ時、あまりにも『作られたいい香り』に、こんな安直な匂いはしないはずと思い、いつか本物を嗅いでみたいと思っていた私は、早速蘭奢待のルーツを検索。翻訳ソフトと身振り手振りで、同じ種類、予想される同産地の香木を手に入れることができました。
帰国して早速、専用の炭の上に銀葉(ぎんよう)を乗せて、香木を置く、いぶされた木っ端から油がジワリと染み出して煙が上がり、心を静めてグッと香りに集中する。思った通り、お土産のお香とは全く違う。ほのかに甘いような、少しツンとする匂いもあって、さらに時間が経つと肌の匂いのような人懐っこさがあって・・・。と、とにかく独特な香り。これだけ香りが溢れた現代に、これ以上の香りはいくらでもあるのだろうけれど、確かにいつもとは違う不思議な香りがそこにあり、それがなんとも魅力的。うかがうに、こうして香りを楽しむ事を聞香と言い、嗅ぐではなく、気持ちを傾けて楽しむことだそう。なんと素敵な言葉。
そういえば、若いご夫婦の依頼でお風呂の壁を桧板にするリフォームを行っています。蒸気の上がった浴室で濡れた壁面からほのかな桧の香りが上がり、目をつぶってその香りを楽しむ。嗅ぐではなく、きっとこれも聞香。思い返せば玄関を開けた時の杉板の香りや土間の微かな土の匂いなど、本来日本の家には素敵な香りが溢れていたような。心を傾けて感じる本物の香りが残る家を残して行きたいと改めて感じた。
(建築士事務所民家・設計部=中津真)
~2025年木族6月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (2)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (2)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (94)
- 酒と家具とインテリア (2)