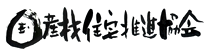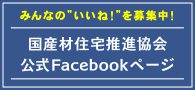酷暑の夏に・・・
【朴訥の論】
39℃という北海道の気温に誰もが驚愕し、地球温暖のひっ迫を突き付けられたようだ。皆様にはこの酷暑をいかがお過ごしでしょうか。
杉・ヒノキを壁や床板として利用して40年になる。当初は乾燥の度合いも甘く、最初に馴染みの居酒屋で壁板として試作したが、乾燥するにつれ實(さね=板と板をつなぐ凸凹)が外れてしまった。ただ、居酒屋は杉板を張り替えることもなく35年の営業を杉板とともに全うした。
これが住宅であれば、風情が良い、味があるなどとは言っておれない。長い年月をかけ板材は乾燥、製材など可能な限り反りや曲がりのない製品均一化の努力を重ね今日に至っている。
当初は節の有る無しで価格差も大きく、節を嫌わずに使うことを推奨していた。ところが板材を生産する側からすれば節ありは抜け節の処理に手間がかかり割に合わない。最近では上小節(小指の先ほどの節)の施工が増えている。
木材は乾燥材であっても冬の乾燥期には痩せ、梅雨時には湿気を吸収し太るため、一年を通して様子をみる必要がある。その調湿効果こそ木材の利点でもある。工業製品であれば痩せも太りもしないため施工性はいいが、調湿効果は薄い。どちらを選択するかは自由であるが、長短含めて理解して欲しいものだ。
陽炎(かげろう)が立つほどの好天気の日に大阪で地鎮祭が行われた。古式に則(のっと)って厳かに執り行われ、参列者それぞれが工事の無事を願った。現地に行くまで気づかなかったが、その場所は36年前に新築を建てた2軒隣だった。ところが通りを探してもその家は見当たらず、2軒隣は更地になっていた。
国産材の活動を始めたころ、事務所下にあった喫茶店のご家族と懇意になり、ご自宅を建て替える相談をいただき、前理事長(故)の熱烈な勧めにより骨太の国産材の家が完成した。ご家族の要望でもあり協会では珍しい洋風の住宅と、吹き抜けにある階段支柱の太い杉丸太が自慢だった。阪神淡路の震災から数年後ご主人が病で亡くなり、夫人は故郷で喫茶店を開業するため、その家を手放された。
解体するには惜しい家であるが、新しく住む人にとっては価値がなかったのだろう。更地と気づいた瞬間、何とも言えない感情が湧きあがり、寂しさがこみ上げる。家にもそれぞれの事情があり、その運命を辿るが、家を解体するということがお施主さんにとってどれほど心痛むことか、今更ながら思い知らされた。
ご無沙汰ばかりの夫人に逢いたくなった。
(国産材住宅推進協会・代表=北山康子)
~2025年木族8月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (2)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (2)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (94)
- 酒と家具とインテリア (2)