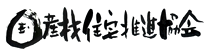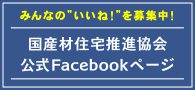小さな声が重なって
【朴訥の論】
先日、富田林の「つながりサポートセンター」さんの改修工事の完成引渡しに同行した。
食品ロスを軽減することと、地域の人の食のサポートとして、不要となっている食材を提供する企業や商店から食材を受け、各こども食堂等に適切に配布することを目的とされている。また、センター内でボランティアによる食堂も運営し、子どもに限らず様々な事情で食に恵まれない高齢者にも提供されるようだ。
ここまでの形に地域をまとめ上げ、行動されていることに感動する。各地で同じような活動が広がりを見せていることが何より嬉しい。
先月、1人いる母方の叔父から電話が入った。
「わし1人になってしもてなぁ」。奥さんは認知症に要介護となり長男の近くにある施設に入所したという。
叔父は高度成長期に腕のいい造付け家具職人として、繁忙な時期を送った人だ。ただ酒癖が悪く母を随分困らせていた。
最初の奥さんは女児(Kちゃん)を未熟児で出産した後、体調が回復しないまま亡くなってしまった。未熟児で生まれたKちゃんは障害児で、医師から長くは生きられないと宣告されていた。
その後、迎えた後妻さんは、Kちゃんに実母と変わらぬ愛情を注ぎ、あれほど周りを困らせた叔父も後妻さんには感謝しかなく、驚くほど穏やかに変化していった。
後妻さんはKちゃんが43歳で亡くなるまで寄り添い、毎日、障害児の作業所まで自転車での送り迎えを欠かさなかった。意識がなくなるまでKちゃんは「お母さん」の手を離さなかったそうだ。
ひっそりと送る家族葬を想像していたが、それを覆すように作業所の先生や友達が花を手向け別れを惜しんだ。
Kちゃんがどれほど多くの人と関わりをもって生きていたかを目の当たりにし、驚きとともに心の和らぎを覚えた。言語もままならないKちゃんが後妻さんにそれほどまでに心を開き、信頼するには、言葉で表せないほどの苦労があったことだろう。
Kちゃんが亡くなり2,3年が経った頃から、糸が切れたように後妻さんの体力は落ち、認知症状が現れたという。叔父は渋ったようだが長男に諭され介護施設に入所された。
考えてみれば叔父夫婦はKちゃんに育まれ、やがてかけがえのない絆で結ばれていったのであろう。Kちゃんの短い人生を輝かせたのは、家族のみならず彼女に触れ合った全ての人たちだった。
こども食堂の大きな功績は、食に留まらず小さな声がけの積み重ねかもしれない。
(国産材住宅推進協会・代表=北山康子)
~2025年木族4月号より~
カテゴリー
- いい木、いい家、いいくらし (1)
- えんがわ (11)
- きの家、木の家、スギの家 (18)
- ごまめの歯ぎしり (2)
- その他 (37)
- その日ぐらし (18)
- 住い考 (24)
- 暮らしのお片付け上手 (1)
- 暮らし下手 (20)
- 暮らし方上手 (73)
- 朴訥の論 (92)
- 酒と家具とインテリア (1)